「報告書作成」が地味に時間を奪う
日々の業務で避けて通れない「報告書作成」。
週報や月報、日々の業務報告など、定期的に提出が求められる書類ですが、「いつも同じような内容を書くのに、地味に時間がかかる…」と感じていませんか?
内容を考えるのに時間がかかるだけでなく、言葉の言い回しや構成を整えるのも意外と手間ですよね。
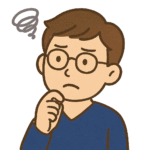
特に毎週・毎月となると、ルーティン作業のはずがストレスの原因になることもあります。
そんな悩みを解決してくれるのがChatGPTです。
ChatGPTを使えば、報告書の“型”となるテンプレートを自動生成したり、自分が書いた内容をわかりやすく整えてくれたりと、作業の負担を大幅に軽減できます。
しかも、自分の業務内容に合わせて柔軟にカスタマイズできるのが魅力です。
今回は、ChatGPTを使って定型報告書のテンプレートを作る方法や、実際のプロンプト例、注意点などを解説します。
報告書作成にかける時間を減らして、より本質的な業務に集中したい方はぜひ参考にしてください。
参考図書をこちらに掲載させていただきます。
ChatGPTでできること|テンプレート作成に最適な理由
報告書のような「定型業務」にこそ、ChatGPTは力を発揮します。
ChatGPTは、あらかじめ条件を伝えるだけで、業務内容や用途に合わせた報告書のテンプレートを自動生成してくれる優れものなんです。
ここでは、なぜChatGPTが報告書のテンプレート作成に向いているのか、その理由を3つ紹介します。
①冗長な表現を自動で整理してくれる
報告書を書く際、「なんとなく長くなってしまう」「表現がくどいかも…」と感じたことはありませんか?
ChatGPTは、伝えたい要点を簡潔かつ分かりやすく表現してくれます。
自分で書いた原稿を添削してもらうこともできるので、読みやすく洗練された文章に仕上がります。
②業務に応じた柔軟なフォーマット生成
営業・経理・開発・マーケティングなど、部署によって報告書の中身は大きく異なります。
「箇条書きで要点だけまとめたい」「定量データを含めたい」などの細かい希望も反映可能です。
③一度作ったテンプレをアレンジ・再利用できる
一度作成したテンプレートを「翌週分として調整したい」「別のプロジェクト用に変えたい」といった場合も、ChatGPTに元の文章を渡して少し指示を加えるだけで簡単にアレンジできます。
テンプレの使い回しが非常に効率的になるため、継続的な業務にもぴったりです。
具体例①|業務報告書のテンプレート生成プロンプト
では実際に、ChatGPTで業務報告書のテンプレートを作ってみましょう。
ここでは、営業部門の週次報告書を例に、プロンプトとその出力例をご紹介します。
以下の条件で業務報告書のテンプレートを作成してください。
・対象:営業部門の週次報告書
・提出先:上司宛
・報告内容:訪問件数、商談状況、成約件数、課題と改善策、次週の目標
・形式:見出しごとに分け、入力欄(●●など)を設けてください
このように「誰向けの」「どんな目的の」「どんな要素を含めたいか」を明確に伝えることがポイントです。
ChatGPTによる出力例
■ 氏名:●●
■ 報告期間:●●年●月●日~●月●日
1. 訪問件数
今週の訪問件数:●●件
2. 商談状況
進行中の商談数:●●件
主な商談内容:
・案件A:●●
・案件B:●●
3. 成約件数と内容
今週の成約件数:●●件
成約内容の概要:●●
4. 課題と改善策
課題:●●
改善策:●●
5. 次週の目標
訪問予定件数:●●件
注力顧客:●●
重点施策:●●
テンプレートの「型」を作ってしまえば楽になる
このテンプレートを一度作っておけば、以後は入力欄に数値や簡単な内容を埋めていくだけで、報告書がすぐに完成します。
また、チームメンバーに配布して、フォーマット統一を図ることも可能です。
もし「箇条書きで簡潔にしたい」「もっと口語調で親しみやすくしたい」などの要望があれば、ChatGPTに追加指示を出すだけで対応可能です。
思い通りのフォーマットにどんどん近づけていけるのが、大きな強みです。
具体例②|週報・月報のフォーマット生成とカスタマイズ
業務報告書と並んで、提出頻度が高いのが「週報」や「月報」です。
定型的である一方で、内容は業務内容やチームによって微妙に異なるため、テンプレ化が意外と難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでもChatGPTを活用すれば、業務に合った形の週報・月報フォーマットを簡単に作成できます。
今回は「事務職の週報」と「マーケティング部門の月報」を例に、それぞれのテンプレート生成とカスタマイズ方法をご紹介します。
例①:事務職の週報テンプレート
プロンプトの例
以下の条件で週報テンプレートを作成してください。
- 職種:一般事務
- 提出頻度:週1回(月曜提出)
- 報告項目:今週の主な業務内容、完了タスク、未完タスク、所感、来週の予定
- 形式:入力欄ありのフォーマット形式で
出力例
【週報(一般事務)】
■ 氏名:●●
■ 報告日:●●
1. 今週の主な業務内容
・●●
・●●
2. 完了したタスク
・●●
・●●
3. 未完了タスクと対応予定
・●●(対応予定:●●)
4. 所感・気づき
●●
5. 来週の予定
・●●
・●●
例②:マーケティング部門の月報テンプレート
プロンプトの例
以下の条件で月報テンプレートを作成してください。
- 部門:マーケティング
- 提出頻度:月末
- 報告内容:キャンペーン実施状況、SNS運用成果、Webアクセス分析、来月の改善方針
- フォーマット:見出し+箇条書き形式で
出力例
【月報(マーケティング部門)】
■ 氏名:●●
■ 対象月:●●年●月
1. 実施したキャンペーン概要
・キャンペーン名:●●
・実施期間:●●
・成果:●●(例:CV率○%、反響○件)
2. SNS運用状況
・Twitter:フォロワー数+●●、インプレッション●●
・Instagram:リーチ●●、保存数●●
3. Webアクセス分析(自社サイト)
・UU(訪問者数):●●
・PV(ページビュー):●●
・離脱率:●●%
4. 来月の改善・注力ポイント
・●●
・●●
フォーマット作成のポイント
- 入力欄(●●)を活用することで、後の記入がスムーズに
- 見出しで内容を明確に分け、読みやすさを意識する
- 自分の業務に合うよう、ChatGPTへの指示内容を少しずつ調整する
テンプレートは「使い回してナンボ」です。
業務や提出先のスタイルに合わせて何パターンか用意しておくと、毎回の作業が一気に楽になります。
一度作ったテンプレを使い回す方法
ChatGPTで一度作成したテンプレートは、使い捨てにするのではなく「使い回す」ことで、より強力な時短ツールになります。
ここでは、テンプレを再利用するための3つのテクニックをご紹介します。
①先週のフォーマットをベースにと伝えるだけでOK
ChatGPTは、以前の出力内容を覚えておくことはできませんが、会話中に前回のテンプレを貼り付けて「この形式をベースに今週分を作ってください」と指示すれば、スムーズに対応してくれます。
先週のテンプレートをベースに、今週分の報告フォーマットを作ってください。
違う点:訪問件数が増えた、重点顧客が変わった、キャンペーン情報を追加したい。
このように「何を変えたいか」だけを伝えれば、ChatGPTが調整してくれます。
②過去のテンプレ+実際の記入例で、より精度アップ
テンプレだけでなく、そこに自分が実際に記入した例も加えて「こんな形でまた来週分を作ってほしい」と指示すると、より実務に即したフォーマットになります。
これは定期報告だけでなく、プレゼン資料や議事録などの繰り返し業務にも応用できます。
③外部ツールとの併用でさらに便利に
ChatGPT単体でも十分便利ですが、以下のようなツールと組み合わせることで、報告業務の効率はさらに高まります。
- GoogleドキュメントやWord
→ChatGPTで生成したテンプレを貼り付けて使いまわせる - NotionやSlackなどの社内ツール
→テンプレートを共有フォルダに保存してチームで使いまわし - Excelと連携(例:ChatGPTに数値要約を依頼)
→データ分析+報告文作成も可能に
Excelとの連携はChatGPTの大きな強みです。
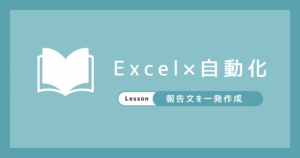
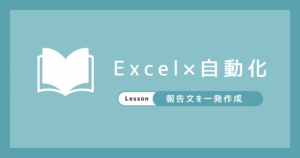


小さな積み重ねが、大きな効率化につながる
テンプレートの再利用を習慣化すれば、「考える時間」と「整える時間」が大幅に短縮されます。
ChatGPTに任せられる部分はどんどん任せ、自分は本質的な業務や判断に集中できる環境を作りましょう。
使うときのコツと落とし穴
ChatGPTは報告書作成の強力な味方ですが、万能ではありません。
効率化を図るためには、正しい使い方と注意点を押さえておくことが大切です。
ここでは、実際に使う際に意識したい3つのポイントをご紹介します。
①あくまで“叩き台”として使う
ChatGPTが生成する文章は非常に自然で、いかにも「それっぽい」文に見えます。
しかし、あくまで参考・下書きとして使うのが基本です。
特に定量データや社内用語などは自分でチェック・修正が必要です。
「AIが作ったものをそのままコピペ」は、思わぬ誤解やミスを生む可能性があるので注意しましょう。
②社内ルールやフォーマットに沿って調整を
企業や部署によっては、「報告書はこのフォーマットで」「この言い回しはNG」といったルールが存在する場合があります。
ChatGPTで作ったテンプレが便利でも、そのまま使うと逆に手間が増えることもあるため、あらかじめ社内の基準を確認しておきましょう。
③機密情報の扱いには十分注意
ChatGPTに入力する情報の中に、機密性の高い内容(顧客名・具体的な案件名など)が含まれる場合は注意が必要です。
社内ポリシーに従い、必要に応じて匿名化・要約してから入力するようにしましょう。
「報告書=つらい」を終わらせよう
毎週・毎月繰り返される報告書作成が正直面倒だ。
そんなモヤモヤを感じていた方も、ChatGPTを活用すれば驚くほどスムーズに業務を進められます。
テンプレートの作成・整形・再利用まで、ChatGPTはまさに“報告書作成の相棒”です。
面倒なフォーマット作成や文章の言い回しはAIに任せて、自分はより重要な業務に集中する。
これが、これからの働き方のスタンダードになっていくと思います。
もちろん、使いこなすにはいくつかの注意点もありますが、逆に言えば“ルールを守ればとても頼れる存在”です。
今後はAIを活用できる人が活躍していく時代になるので、少しずつ勉強しておくことが重要になってきます。
独学では続かないという方はDMM 生成AI CAMP等の便利な学習サービスを活用するのも一つの手だと思います。
その前にまずは、あなたの業務に合った報告書テンプレートを一つ作ってみてください。
数分で完成するそのひな形が、これからの業務時間を何時間も節約してくれるはずです。
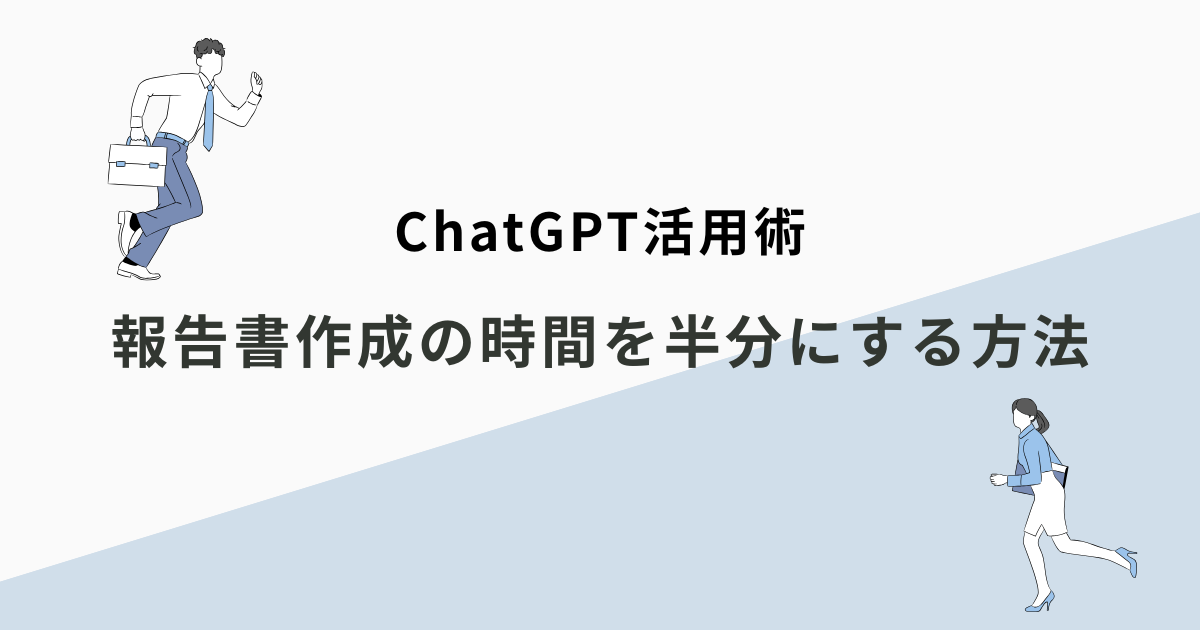


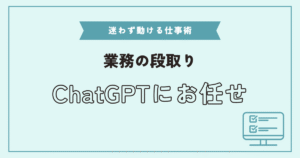
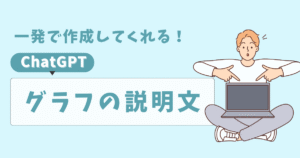
コメント