プレゼン原稿がつらい…なんてことないですか?
プレゼン資料はできたのに、発表用の原稿が全然書けない…。
そんな経験、ありませんか?
話す順序が決まらない、時間内に収まらない、言葉が固すぎる、などなど。
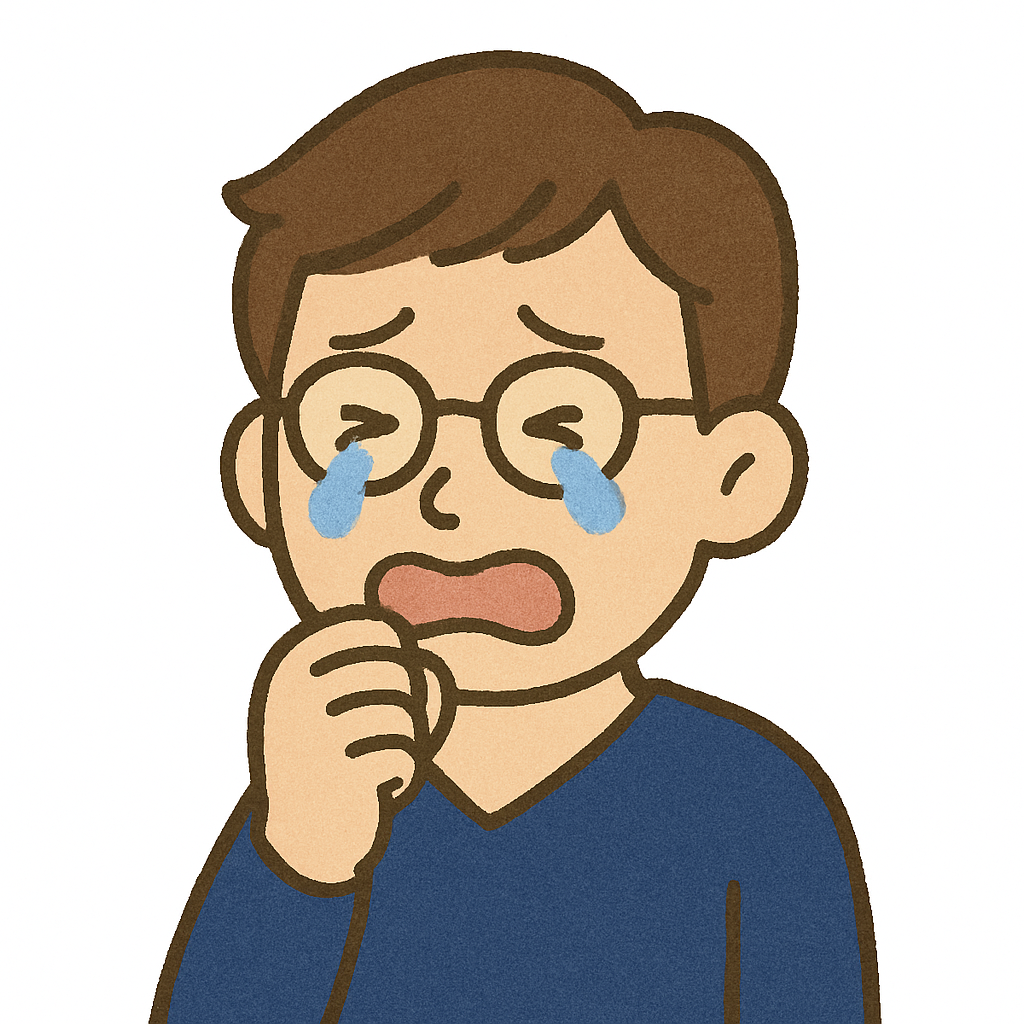
アドリブが苦手な私はこの「原稿づくり」でつまずいていました。
でもある日、ふとChatGPTに頼んでみたら、わずか数十秒で自然な原稿が完成。
「もっと早く使っていれば…」と本気で思いました。
この記事では、そんな私の体験をもとに、ChatGPTで原稿を秒速作成する方法をご紹介します!
ChatGPTに頼んだら「秒」で原稿ができた
原稿がなかなか進まず、プレゼン本番が近づくばかり…。
そんなとき、ふと思い立ってChatGPTに「このスライドの要点をもとに、3分間の発表原稿を作ってください」と頼んでみました。
スライドの内容は箇条書きで入力するだけ。指示はそれだけでした。
すると、わずか数秒で“話すため”の原稿が完成。
驚いたのは、その内容が単なる読み上げではなく、しっかりと口調が整った話し言葉になっていたことです。
「皆さんは“生成AI”という言葉を聞いたことがありますか?」と自然な問いかけから始まり、スライドの要点が無理なくつながっていました。
下書きを自分で1から書くよりも圧倒的に早く、調整も一言で済む。
もう原稿づくりの負担は激減です。
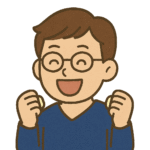
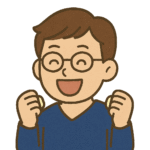
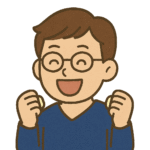
正直、自分で書くより、ChatGPTに頼んだ方が早くて伝わりやすいです
【プレゼン原稿】自分で書くより早くて分かりやすい!
ChatGPTを使う前、私の原稿作成はとにかく時間がかかっていました。
伝えたいことをうまく言語化できず、書いては消してを繰り返す…。
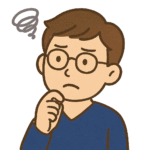
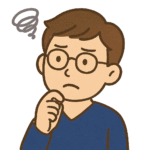
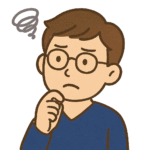
気がつけば1時間以上経っている、というのがいつものパターンでした。
でも、ChatGPTを使ってからは、作業の進め方ががらりと変わりました。
実際のステップはこんな感じです。
【Step 1】スライドの要点を箇条書きで用意
まず、プレゼン資料を見ながら、各スライドの内容を簡単にまとめます。
たとえば「生成AIとは?」というスライドなら、
- テキストや画像を自動で作るAI
- ChatGPTやClaudeなどが有名
- 「調べる」「まとめる」「書く」が得意
といった具合です。
完璧でなくてもOK。メモ書きレベルで十分です。
【Step 2】ChatGPTにプロンプトを入力
続いて、ChatGPTに以下のように依頼します。
以下のスライドの要点をもとに、3分程度のプレゼン原稿を作ってください。話し言葉で、初心者にもわかりやすくお願いします。
・テキストや画像を自動で作るAI
・ChatGPTやClaudeなどが有名
・「調べる」「まとめる」「書く」が得意
【Step 3】生成された原稿を確認・微調整
数秒後に原稿が出てくるので、実際に声に出して読んでみます。
今回はこんな感じで出力されました。
プレゼン原稿
こんにちは。今日は、最近よく耳にする「AIでテキストや画像を作る技術」について、カンタンにご紹介したいと思います。
まず、今注目されているのが「生成AI」というものです。これは、人が入力したキーワードや質問に対して、AIが自動で文章を書いてくれたり、画像を作ってくれたりする技術なんです。
たとえば「ChatGPT」や「Claude(クロード)」という名前を聞いたことがある方もいるかもしれません。これらは、代表的なAIのサービスで、会話するように使えるのが特徴です。
じゃあ何ができるのか?というと、たとえばこんなことが得意です。
ひとつめは「調べること」。たとえば「来週の天気は?」とか、「ある企業の特徴を教えて」といった質問に対して、インターネットの情報を元にわかりやすく答えてくれます。
ふたつめは「まとめること」。たとえば、長いニュース記事や会議のメモを、短くスッキリまとめてくれるんです。
そして、みっつめは「書くこと」。文章を書くのって意外と時間がかかりますよね。でもAIなら、たとえば「営業メールを書いて」とか「企画書のアイデアを出して」と言うだけで、ぱっと文章を作ってくれます。
つまり、AIは「調べる・まとめる・書く」といった、これまで人が時間をかけていた作業を、すごくスピーディーに手伝ってくれる存在なんです。
もちろん、まだまだ完ぺきではないので、使うときはちょっと確認が必要ですが、うまく使えば毎日の仕事や勉強がぐっと楽になります。
今日はほんのさわりだけでしたが、「あ、こんなこともAIに頼めるんだな」と思っていただけたら嬉しいです。
ありがとうございました。
もし「ちょっと固いな」「もう少し柔らかい表現にしたいな」と思ったら、ChatGPTにこう伝えます。
「もっとカジュアルな口調にして」
「ですます調にして」
「5分用に少し長めにして」
といった形で、何度でも調整が可能です。
スライドだけあっても、何をどう話せばいいか分からず、時間だけが過ぎる…
こう使えばもっと便利!応用アイデア
ChatGPTにプレゼン原稿を作ってもらうだけでもかなり便利ですが、実はちょっとした工夫で、さらに使い勝手が良くなります。
ここでは、私自身が試して効果的だった応用アイデアをご紹介します。
発表時間に合わせて“長さ調整”してもらう
プレゼンの持ち時間に応じて、「3分用に」「5分バージョンで」といった指示を出すと、時間にぴったりの分量で原稿を生成してくれます。
しかも、「少し短く」「半分の長さに」など、ざっくりした指示でも対応可能です。
時間オーバーの不安がなくなるのはかなり心強いです。
スライドごとに分けて原稿を作成
「スライド1枚ずつナレーションをつけてください」と伝えると、スライド単位でコメントを整理してくれます。
これは資料を見ながら話す場合にとても便利です。
あとでスライドをめくるタイミングに合わせて練習できるので、本番の安心感も違ってきます。
自分らしい“話し方”に寄せる
「もう少しフレンドリーに」「上司に話すような丁寧な口調で」など、トーンやキャラを変えることも可能です。
私はよく、「初心者向けに、やさしい言葉で」「親しみやすく」とお願いしています。
自分らしい話し方をベースにした原稿が手に入るので、読み上げても違和感がありません。
よく使うプロンプトを“定型化”する
何度か使っているうちに、よく使う指示文が見えてきます。
たとえば私は、
以下の箇条書きをもとに、3分のプレゼン原稿を話し言葉で作ってください。やさしく自然な口調でお願いします。
というプロンプトをテンプレートとしてメモしておき、毎回コピペで活用しています。
自分なりの“型”ができると、原稿作成がさらにスピーディーになります。
注意点とコツ
ChatGPTはプレゼン原稿づくりにとても便利なツールですが、そのまま使えば完璧というわけではありません。
よりよい原稿に仕上げるためには、いくつかの注意点とコツがあります。
必ず“声に出して”確認する
まず大事なのが、生成された原稿は必ず声に出して読むこと。
見た目には自然に見えても、話してみると「長すぎる」「言いづらい」と感じることがあります。
とくにプレゼンは“読む”ものではなく“話す”ものです。
実際に話してみて、テンポや言葉の響きをチェックするのがポイントです。
自分の言葉に少しだけ“寄せる”
ChatGPTの原稿は、全体としては自然でも、ところどころ「自分っぽくない」表現が混じることがあります。
そんなときは、言い回しを少し変えるだけで一気に自分らしくなります。
たとえば、「〜でございます」→「〜です」に変えるなど、小さな調整だけでもOKです。
専門用語や固有名詞には補足を
プレゼンのテーマによっては、専門用語や略語、社内用語が含まれることもあると思います。
ChatGPTは一般的な内容には強いですが、業界固有の表現や最新の社内情報まではカバーできないことがあります
「これは知らない人に伝わるかな?」と一度立ち止まる意識が大切です。
丸投げせず「方向性」を伝える
最初に「どういう雰囲気で話したいか」「誰に向けた発表なのか」をしっかり伝えると、より的確な原稿が出てきます。
たとえば、「初心者にやさしく説明したい」「上司への報告プレゼン」など、相手や目的を明確にしておくことが、満足度の高い出力につながります。
ちょっとした意識と調整で、ChatGPTはさらに頼れる「原稿アシスタント」になります。
うまく使えば、原稿づくりのストレスからかなり解放されますよ。
プレゼン原稿は秒で作れる!
プレゼン原稿づくりに何時間もかかっていた私にとって、ChatGPTとの出会いはまさに“革命”でした。
スライドの要点を渡すだけで、数十秒後には話し言葉の原稿が完成します。
そこに少しだけ自分の色を加えるだけで、堂々と話せる発表が形になります。
でも、それを含めても、作業時間も、負担も、比べものにならないほど軽くなるのは間違いありません。
プレゼン前の「原稿が進まない…」という悩みが、ChatGPTで一気に解消されるかもしれません。
「話す内容がまとまらない」「時間がない」そんな方こそ、一度試してみてください。
あなたの原稿づくりが、驚くほどスムーズになるはずです。
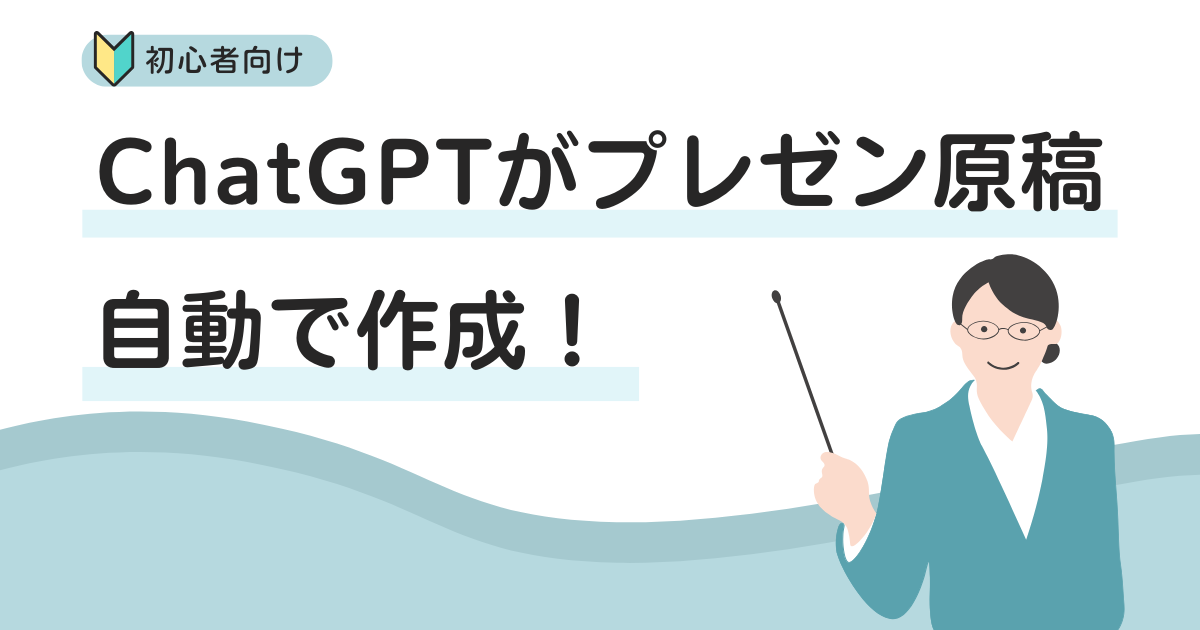
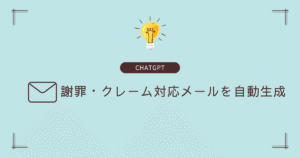

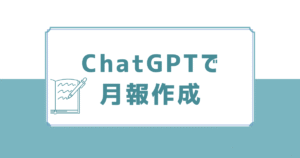

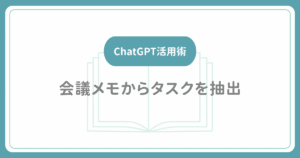
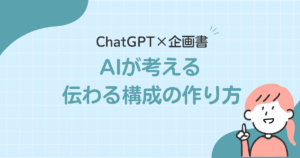
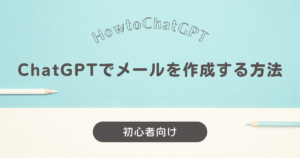
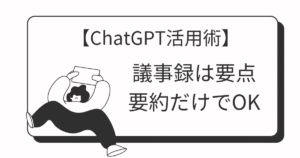
コメント